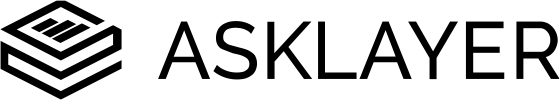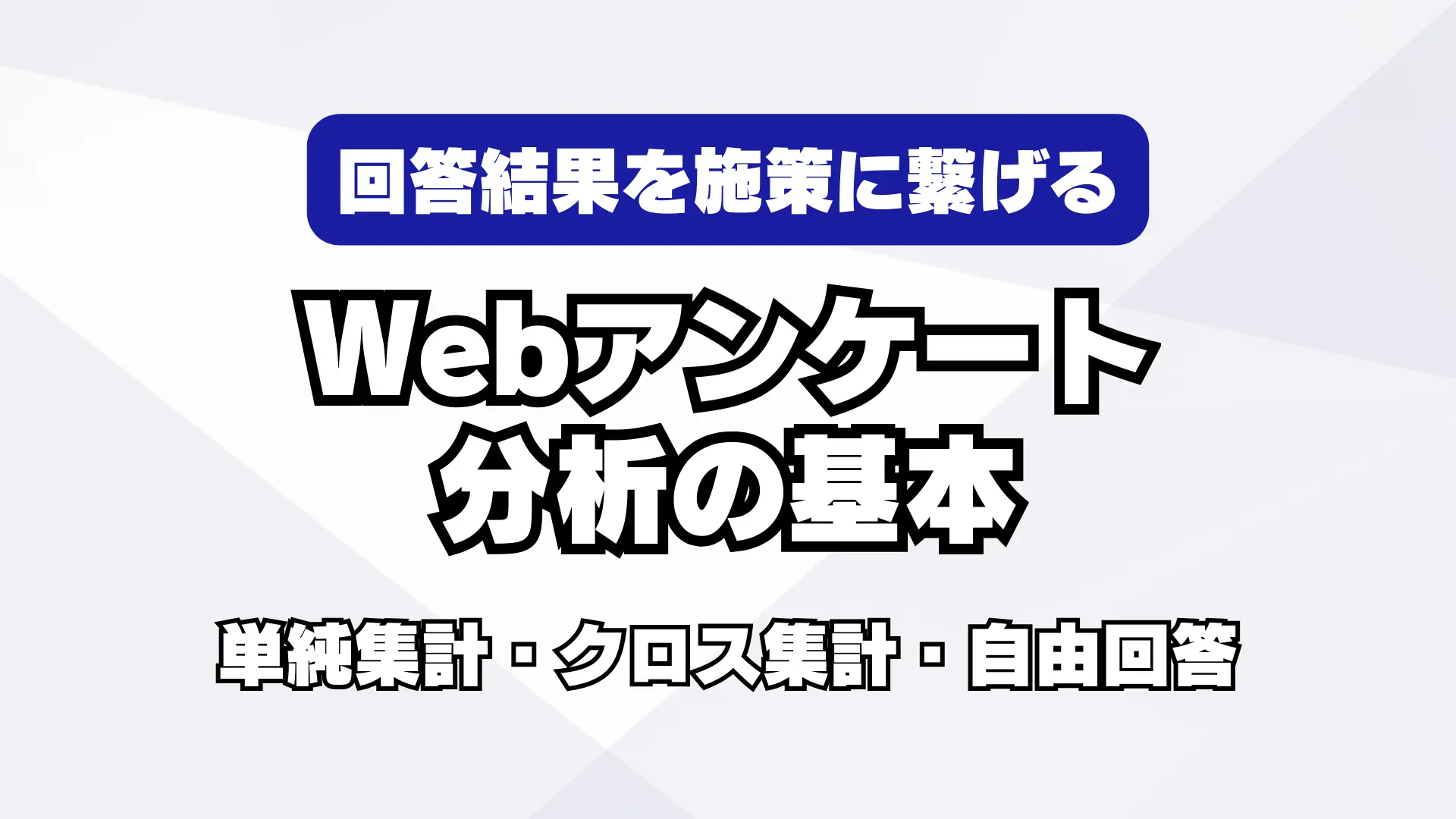
Webアンケート分析でビジネスに応用できる洞察を導き出す
Webアンケート結果の数字だけで、「どう応用すればよいのか」は分かりません。
しかしながら「満足と答えた人が7割でも、年代別に分けると20代では不満が目立つ」というように見方を変えるだけで、ビジネスに応用することが可能になります。
本記事では、Webアンケートの結果を「どう整理し、どう読み解くか」を、実務に役立つ基本ステップとしてわかりやすく解説します。


正しい分析でアンケート結果をビジネスに役立てる
Webアンケート 分析前にやっておくべき準備とは?
回答が集まり、分析を行う時点でデータが未整理のままでは、正しい結論が得られないことがあります。
まずは データを整える“ひと手間” をかけることで、あとからの集計や比較がスムーズになり、結果に自信を持てるようになります。
以下にアンケート分析の前準備の手順をご紹介します。
1.重複回答を取り除く

同じ人が複数回答えていないかを確認します。
【例】
同じメールアドレスから2回送信されていたら、最初の1件だけを残す。
2.「未回答」の扱いを決める
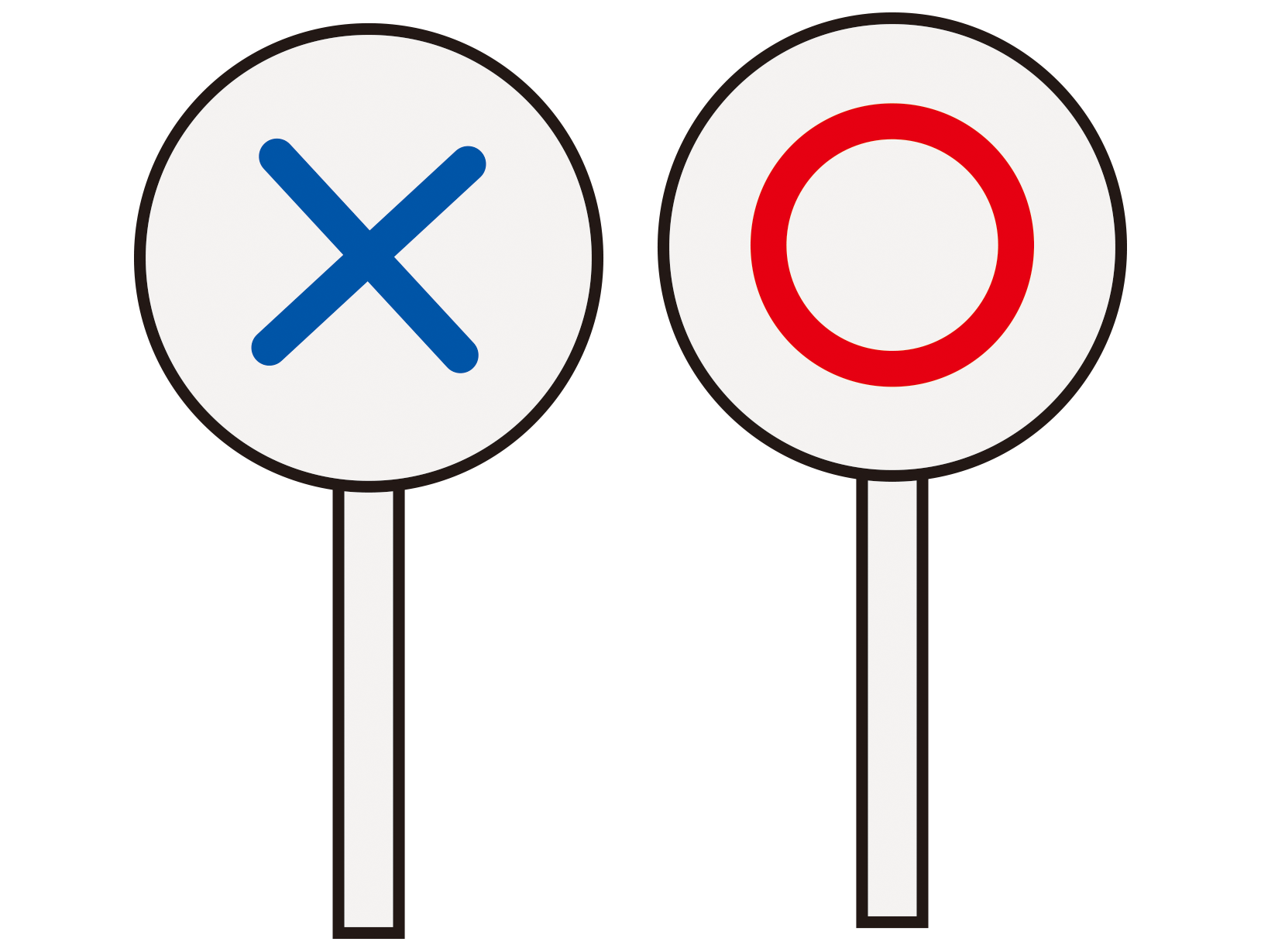
選択肢を飛ばしてしまった「空白」の回答がある場合は、集計から外すか「未回答」として別にまとめましょう。
【例】
「年齢」欄が空白の人は分析対象から除外する。
3.極端な値を確認する

満足度10点満点の設問で、ほとんどが5〜8点なのに「1点」や「10点」が大量にあるときは注意が必要です。
入力ミスやいたずらの可能性もあります。
4.サンプル数を確認する
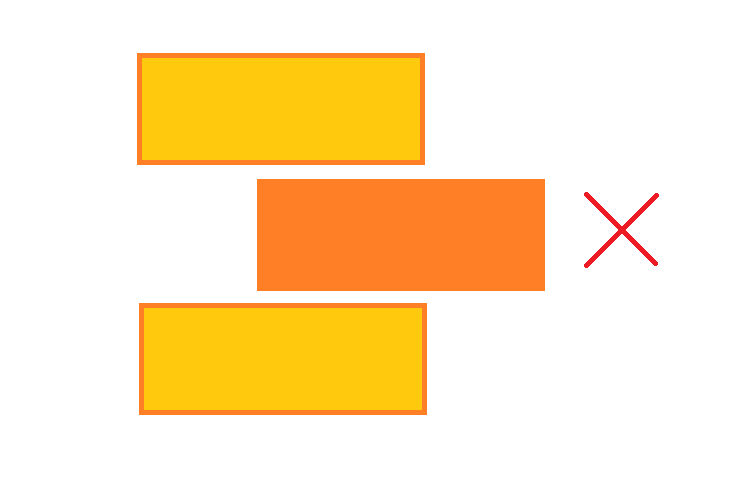
グループごとの人数が少なすぎると結果は安定しません。
目安として各グループ20〜30件以上あると安心です。人数が足りない場合は区分をまとめるか、「参考程度」と明記して使いましょう
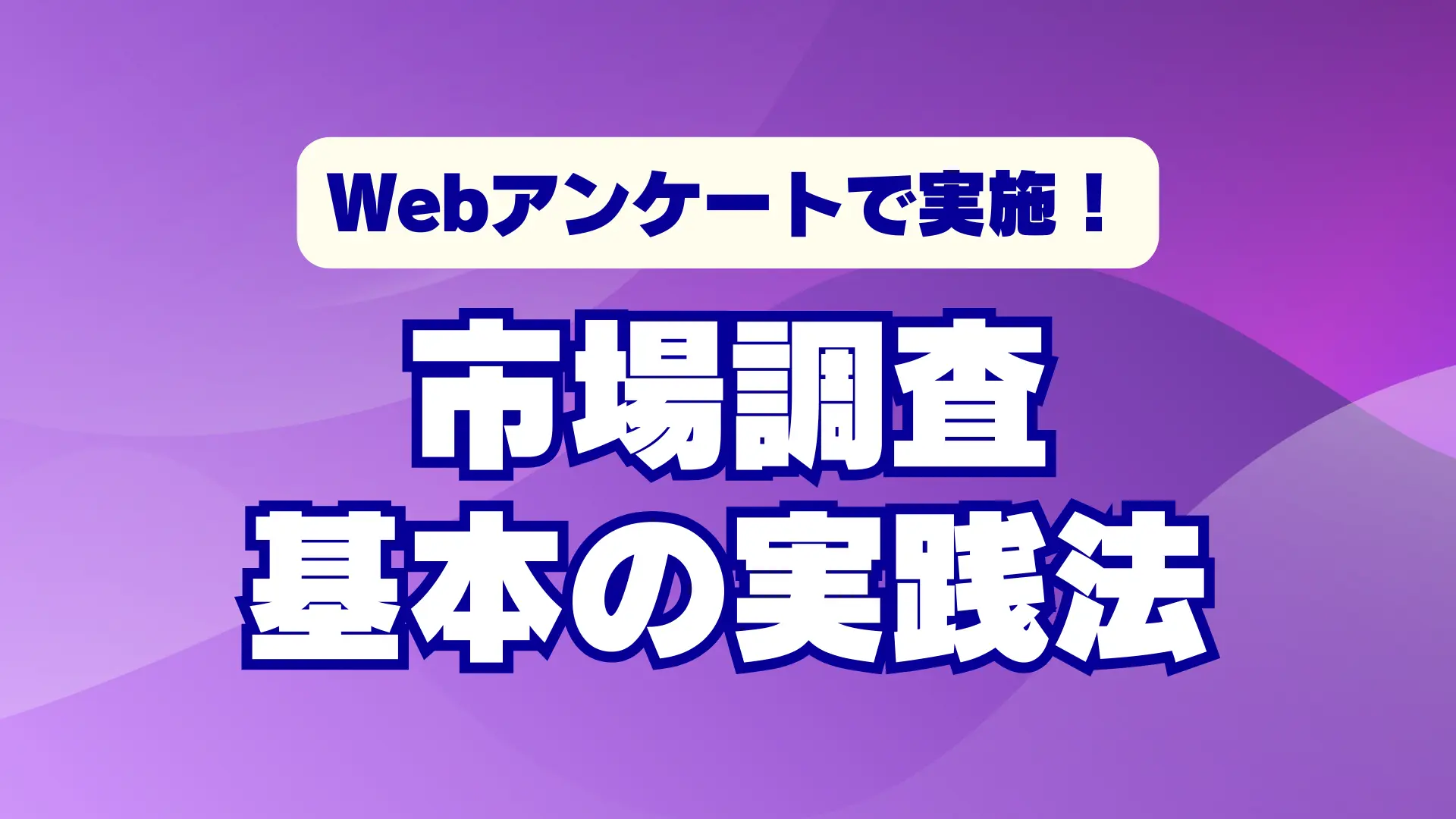
【市場調査の基本が分かる記事】
市場調査の実践法|顧客の声を集める
この記事では、市場調査の目的や種類、代表的な手法、費用や期間の目安、調査設計の基本までを体系的に解説します。
Asklayer.io
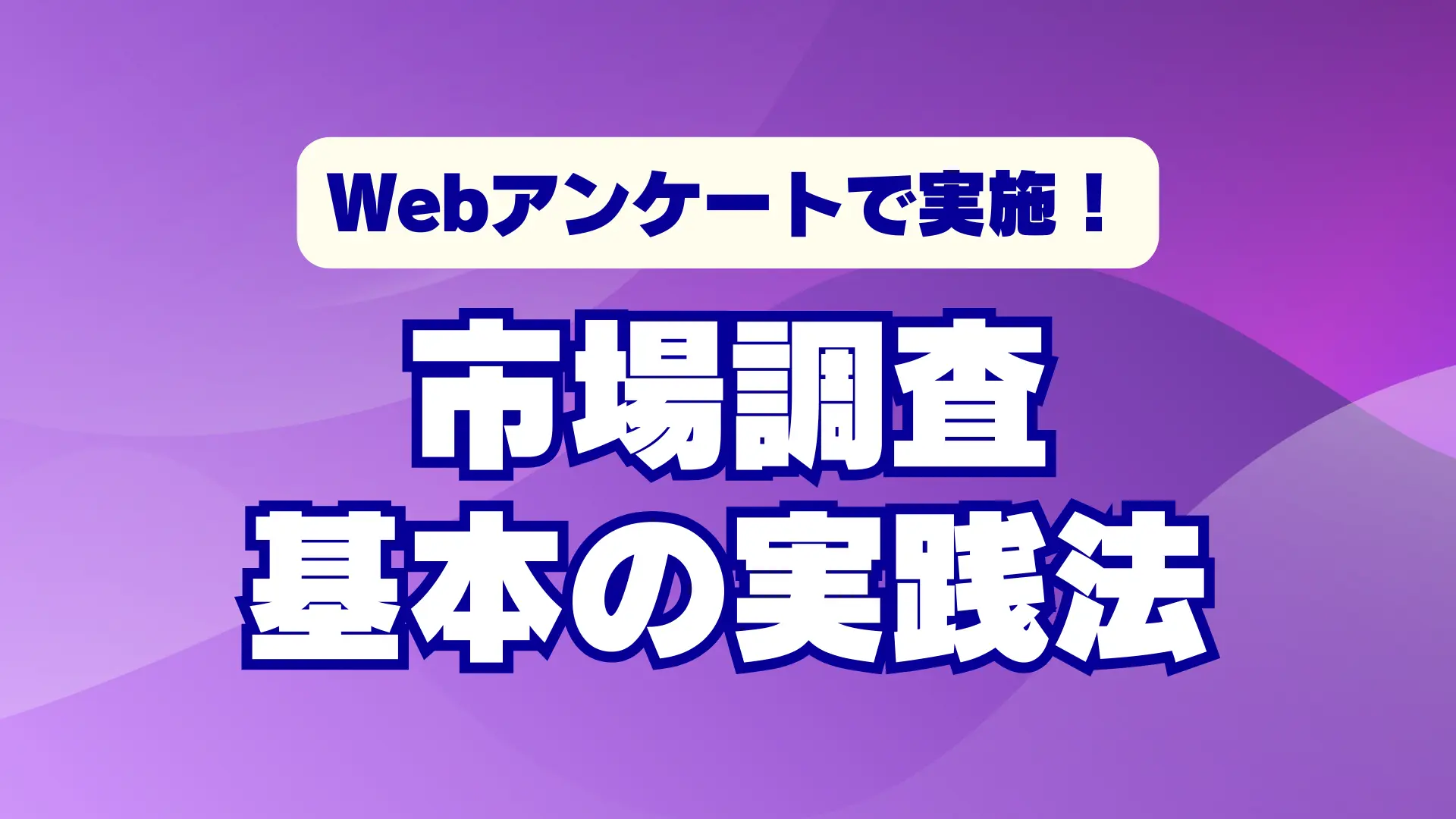
【市場調査の基本が分かる記事】
市場調査の実践法|顧客の声を集める
この記事では、市場調査の目的や種類、代表的な手法、費用や期間の目安、調査設計の基本までを体系的に解説。
Asklayer.io
Webアンケート分析 結果の全体像を掴む
まずは回答をシンプルに数えて、全体の傾向をつかみましょう。
選択肢ごとの人数や割合、平均値や中央値など、基本的な数値を確認するだけでも「どの意見が多いのか」「全体の満足度はどの程度か」が見えてきます。
1.選択肢ごとの割合を出す
各質問の各回答が、全体の何割を占めるかを確認します。
全体の傾向を一目で把握でき、最も多い意見がどれかが分かります。
【例】
「この商品に満足しましたか?」
・満足=70%
・どちらでもない=20%
・不満=10%
→ 多くのお客さまは満足しているが、不満を持つ層も一定数いると分かります。
2.平均値と中央値を確認する
数値で答える設問は「平均値」と「中央値」をセットで見るのが基本です。
平均値は、すべての回答を足して回答数で割ることで算出できます。
Excelの計算式は 【=AVERAGE[セル範囲]】
また中央値は、回答の値を小さい順に並べて、真ん中に来る数値です。
Excelの計算式は 【=MEDIAN[セル範囲] 】
平均値は全体の傾向を表し、中央値は“真ん中の人”を示すので、この両方を見ることで評価の偏りを判断できます。
【例】
「満足度を1〜10点で評価してください」
・平均点=6.8点
・中央値=7点
→ 平均と中央値が近いので、全体的に安定した評価が多いと判断できます。
3.最頻値(モード)を見る
最も多く選ばれた値(最頻値)を見ると、“典型的な答え”を知ることができます。平均値とは違う気づきが得られることもあります。
【例】
満足度の回答が「5点」に最も多く集まっていた場合。
→ 平均点は6.8でも、最も多い典型的な顧客は「5点」と評価していると分かります。
アンケート結果の分析は、9割は設計の精度で決まります。詳細は、設計手順ガイドへ。

【アンケート設計と回答率向上に役立つ記事】
Webアンケートの設計手順|回答率が上がる5ステップ
この記事では、設問タイプの選び方や表示トリガー(離脱時・滞在秒数)、質問数・所要時間の目安からプライバシー対応まで、実務に役立つWebアンケートの設計を5ステップを解説します。
Asklayer.io

【設計と回答率向上に役立つ】
Webアンケートの設計手順|回答率が上がる5ステップ
この記事では、設問タイプの選び方や表示トリガー(離脱時・滞在秒数)、質問数・所要時間の目安からプライバシー対応まで、実務に役立つWebアンケートの設計を5ステップを解説します。
Asklayer.io
Webアンケート分析 クロス集計
全体の傾向をつかんだら、次は「どのグループがどう答えているか」を比べてみましょう。
クロス集計は、全体だけでは見えない違いを明らかにします。「誰が満足しているのか」「どの層に課題があるのか」を把握することで、改善策を具体的に考えやすくなります。
クロス集計とは?
クロス集計とは、2つ以上の項目を組み合わせて答えを比べる方法です。
これにより、グループごとの違いを発見することが可能です。(誰が満足しているのか、不満はどの層に多いのかなど)。
【例】
「性別 × クーポン利用率」
「年代 × 満足度」
【注意点】
グループを細かく分けすぎると、人数が少なくなり結果が不安定になります。最低でも各グループに20〜30件以上あるかを確認しましょう。
◆クロス集計の具体例
【具体例1】性別 × クーポン利用率
性別 男性
クーポン利用率 35%
性別 女性
クーポン利用率 60%
全体平均では50%でも、性別で分けると女性の利用率が明らかに高いことが分かります。
→ 【施策のヒント】「女性向けキャンペーンではクーポンを強調する」など。
【具体例2】年代 × 顧客満足度
年代 20代
満足度平均 5.8点
年代 30代
満足度平均 7.0点
年代 40代以上
満足度平均 7.2点
全体平均は6.8点ですが、20代に絞ると不満が目立ちます。
→ 【施策のヒント】「20代向けに配送スピードや価格訴求を改善」など。
教育分野で使える授業アンケート質問テンプレートはこちら。
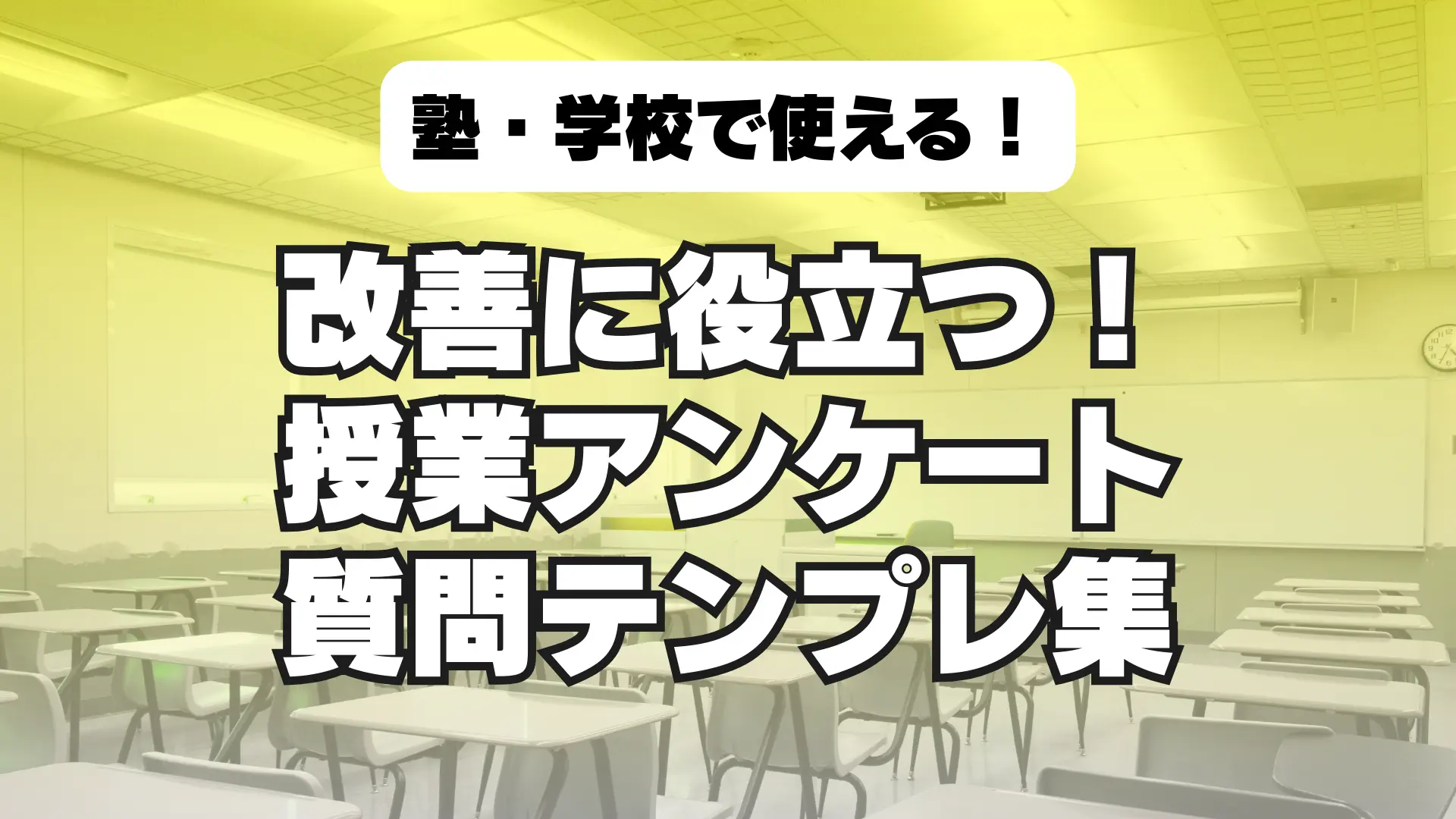
【授業アンケート作成に役立つ記事】
授業アンケート作成方法|塾・大学・高校向け質問テンプレート
この記事では、大学・高校・塾で使える授業アンケートの無料テンプレートと質問例をまとめました。実装手順、回答率を上げる工夫まで、今日からそのまま活用できる内容を解説します。
Asklayer.io
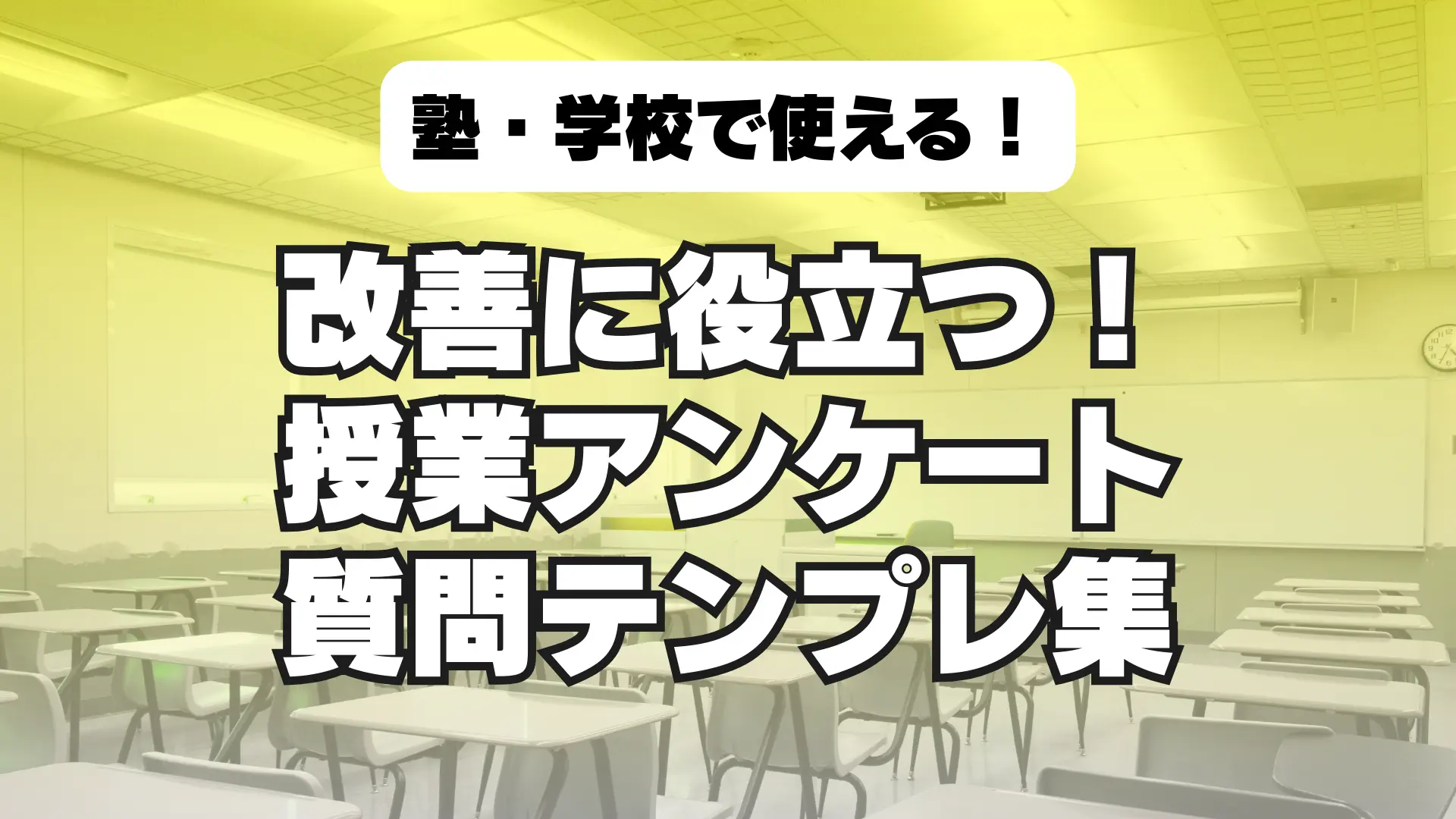
【授業アンケート作成に役立つ】
授業アンケート作成【高校・大学・塾】
この記事では、大学・高校・塾で使える授業アンケートの無料テンプレートと質問例をまとめました。実装手順、回答率を上げる工夫まで、今日からそのまま活用できる内容を解説します。
Asklayer.io
【具体例3】新規顧客 × リピーター
属性 新規顧客
不満率 25%
属性 リピーター
不満率 8%
リピーターは満足度が高い一方、新規顧客に課題があることが分かります。
→ 【施策のヒント】「初回購入の体験を改善する」など。
Webアンケート分析 Asklayerなら難しくない!
Excelでのクロス集計やグラフ作成に時間をかけていませんか?
Webアンケートツール・Asklayerなら、回答収集から集計・レポート化までを自動で実行。
誰でもすぐに「使えるデータ」に変えられるから、分析に迷う時間をなくせます。
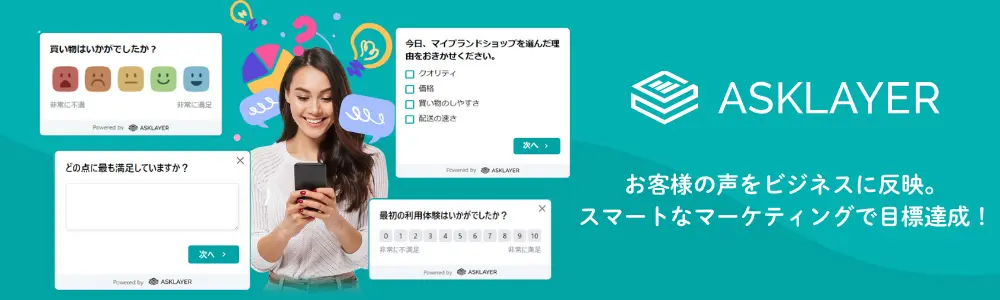

登録1分・テンプレ多数!
高回答率アンケート!
初期費用は不要。
今すぐ施策を開始!
・自動プロファイルでリード獲得。
・完全モバイル対応。
・疑問はチャットサポートで解決。
Webアンケート分析 有意差のチェック
クロス集計でグループごとの差が見えてきたとき、その違いが“本当に意味があるのか”を確かめるのが有意差のチェックです。
これは本来、統計の手法を使って「偶然ではなく差がある」と判断する工程です。実務ではクロス集計だけでも十分役立ちますし、必要に応じてExcelや専門ソフトで確認すれば安心です。
Excelを使った有意差の算出方法(簡易版)
割合の比較(男女など)
→ =CHISQ.TEST(実測範囲, 期待値範囲)
2グループの平均比較(施策前後など)
→ =T.TEST(範囲1, 範囲2, 2, 2) ※両側・等分散の場合
3グループ以上の平均比較(年代別など)
→ [データ] → [データ分析] → 分散分析(ANOVA)
Webアンケート分析 自由記述の分析
アンケートには選択肢だけでなく「自由記述」も含まれることがあります。
自由記述は数値化しにくい反面、顧客の本音や改善のヒントが直接書かれている大切な情報です。これらを読み解くことで、
「お客様が何に満足し、どこに不満を持ち、何を望んでいるのか」
が見えてきます。単に読み流すのではなく、整理して活かすことで数値データを補い、より具体的な改善につなげられます。
◆自由記述の分析方法と例
【例1】タグ化して分類する
コメントを「配送」「価格」「サポート」「品揃え」などテーマ別に分ける。
「荷物が予定日より遅れた」→「配送」
「もう少し安ければ嬉しい」→「価格」
→多く集まったタグを確認すれば、改善すべき領域が一目で分かる。
【例2】頻出語を数える
自由回答内によく出てくる単語や語句を数えて、ポイントを探る。
「梱包が丁寧」「梱包がきれい」というコメントが多い
→ 強みとして訴求できる
「サイズがない」「サイズ展開が少ない」という声が多い
→ 品揃えの改善が急務
【例3】感情分析
回答から感情を「ポジティブ」「ネガティブ」「要望」の3種類に分類する。
「また利用したいです」→ポジティブ
「価格が高い」→ネガティブ
「もっと色のバリエーションを増やしてほしい」→要望
→このように分類すると「喜ばれている点」「不満点」「次の改善アイデア」が整理されます。
Webアンケート分析結果を施策に繋げるには
アンケート回答の分析で大切なのは、そこから具体的な改善策に結びつけることです。
単純集計やクロス集計、自由記述から得られた気づきをもとに、「次に何をするか」を整理しましょう。以下に、アンケート結果の活用についてステップごとに解説します。
1.強みを活かす
良い評価が多い点は、自社の強みとして打ち出せます。
【例】
「梱包が丁寧」という声が多ければ、商品ページや広告で「丁寧な梱包」をアピールする。
2.課題を改善する
不満が集まる点は、最優先で直すべき課題です。
【例】
「配送が遅い」という意見が多ければ、配送業者の見直しや発送体制を改善する。
3.要望を取り入れる
お客様の要望は次の施策や新商品に生かせます。
【例】
「もっと色のバリエーションが欲しい」という声があれば、次回の商品企画に反映する。
4.社内で共有する
分析結果は担当者だけでなく、関係部署にも共有して活用しましょう。
【例】
満足度アンケートの結果を社内会議で発表し、商品チーム・CSチームで役割分担して改善策を決める。
アンケート回答の保存期間や第三者提供の扱いは、データのプライバシーポリシーで整理しましょう。
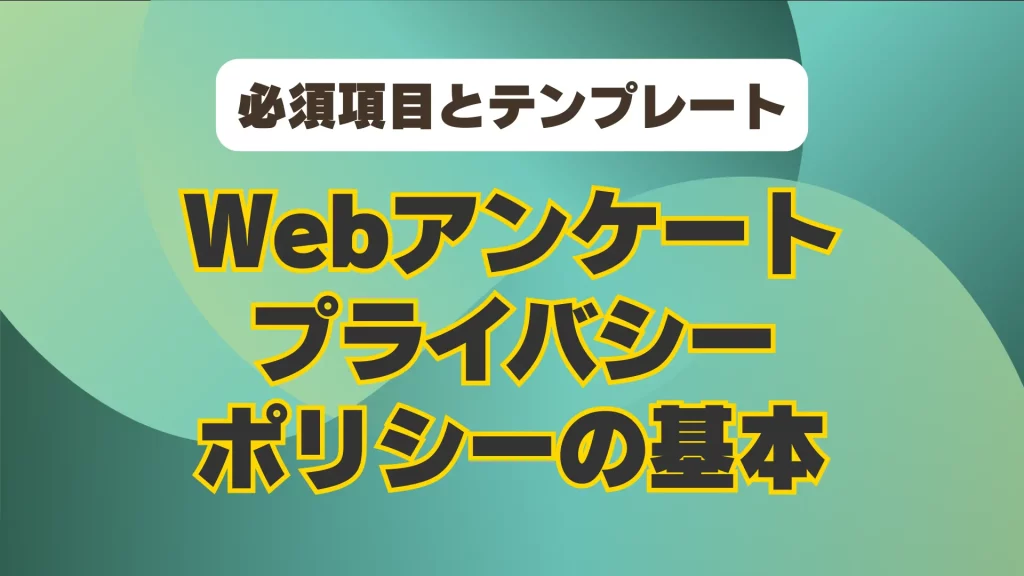
【プライバシーポリシー策定に役立つ記事】
プライバシーポリシーの必須項目と書き方ガイド
Webアンケートに欠かせないプライバシーポリシー。その必須項目と書き方を、すぐ使えるテンプレートを交えて解説しています。
Asklayer.io
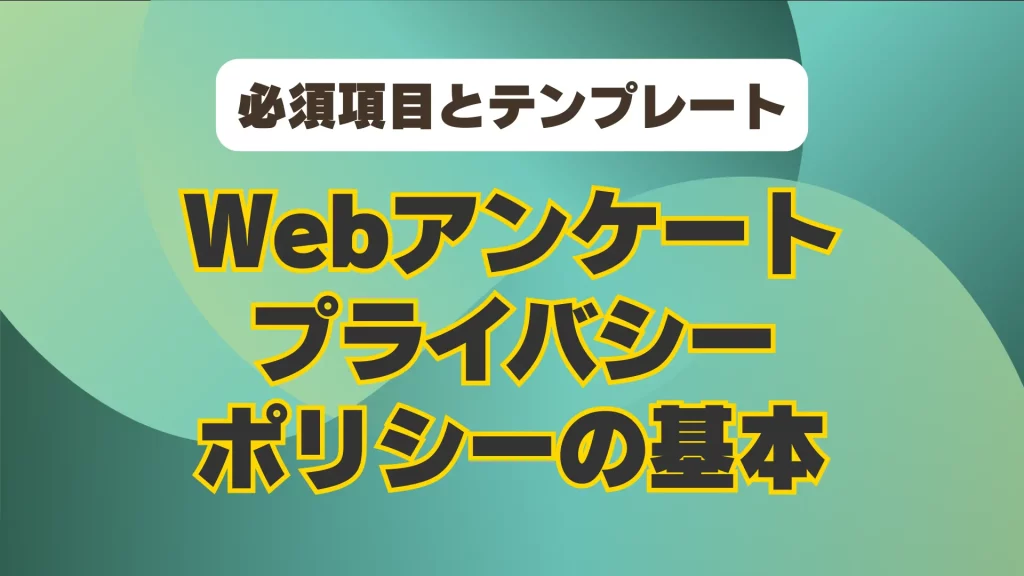
【プライバシー対応に役立つ記事】
プライバシーポリシーの必須項目と書き方ガイド
Webアンケートに欠かせないプライバシーポリシー。その必須項目と書き方を、すぐ使えるテンプレートを交えて解説しています。
Asklayer.io

【アンケート回答率・回収率向上に役立つ記事】
Webアンケートの回答率を向上させる6つの秘訣
アンケートの成功は大きく回答率に依存しており、高い回答率を達成することはしばしば難しい課題です。回答率を向上させるヒントとは?
Asklayer.io

【アンケートの回答率向上に役立つ記事】
Webアンケートの回答率・回収率を向上させる6つの秘訣
アンケートの成功は大きく回答率に依存しており、高い回答率を達成することはしばしば難しい課題です。回答率を向上させるヒントとは?
Asklayer.io
Webアンケートの結果分析に関するFAQ
アンケート分析はなぜ必要ですか?
アンケートは集めるだけでは意味がなく、結果を分析して初めて改善点や強みが見えてきます。分析を通じて「顧客が満足している理由」「不満の原因」「次に求められる改善」が明確になり、施策に結びつけられます。
アンケート結果はExcelで分析できますか?
はい、可能です。Excelの集計機能やピボットテーブルで単純集計やクロス集計を行えます。さらに =T.TEST() や =CHISQ.TEST() などの関数を使えば有意差の確認も可能です。専用ツールがなくても基本的な分析は十分対応できます。
アンケートの自由記述はどう分析すればいいですか?
コメントを「配送」「価格」「サポート」などのテーマに分けてタグ化し、頻出するキーワードや感情の傾向を整理します。たとえば「配送が遅い」という意見が多ければ改善の優先度が高いと分かります。
有意差とは何ですか?初心者でも扱えますか?
有意差とは、グループ間の差が「偶然ではなく本物か」を確認する考え方です。難しい計算はExcelやアンケートツールに任せればOKです。基本は「差を見つけたら、本当に意味があるか確かめる工程がある」と理解すれば十分です。
専門知識がなくてもアンケート分析はできますか?
はい。単純集計やクロス集計は誰でも始められる基本的な方法です。難しい統計知識がなくても、「全体像をつかむ → グループごとに比べる → 自由記述を読む」という流れで実務に役立つ分析が可能です。
アンケート分析を効率化する方法はありますか?
Excelで手作業する方法もありますが、時間がかかります。AsklayerのようなWebアンケートツールを使えば、回答収集からクロス集計・グラフ作成まで自動化でき、分析をスムーズに進められます。
Webアンケート結果を分析 ビジネス向上に役立てる
アンケート結果の分析は、アンケート回答から得られた洞察をビジネスに応用するための大切なステップです。
まず、得られたデータから不要と思われる回答のクリーニングを行い、その後多角的に結果を分析する必要があります。得られたデータを深く掘り下げて行きます。
またビジネス改善サイクルを作り、定期的にアンケート調査を行うことで、ユーザーの動向やトレンドにキャッチアップできます。Webアンケート結果をビジネス向上に役立てましょう。
今すぐはじめよう!
リスクなしで
Webアンケートを
実施しよう
無料アカウントを作成して、Asklayerのアンケート機能をあなたのWebサイトでお試しください。
クレジットカード登録は必要ありません。